司法書士試験の基本書は大学のテキストとは違う
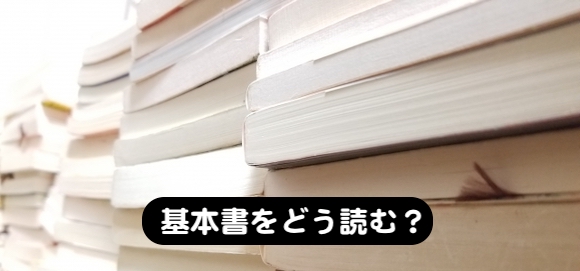
司法書士試験に合格するには、大量の知識を効率よく覚えて身につける必要があります。
基本書というと、大学では法律学者が書いた日本語?と思われるような本をイメージますが、司法書士試験の基本書という意味では全く違います。
大学で使う基本書を読み込んでも、司法書士試験には合格しません。
司法書士試験の基本書とは、試験に出る内容に特化した、効率よく勉強できる教科書のことです。
ここでは、司法書士試験の基本書を効率的に使いこなす勉強方法を紹介しています。
司法書士試験の基本書は薄い本を買って使いこなす
まず、自分に合った基本書をどう見つけるかです。
書店に行くと司法書士試験の受験図書がたくさん出版されています。
「これで万全」といった分厚いものから、「2週間でわかる」というようなコンパクトなもの、イラストや漫画で一見わかりやすそうに書いてあるものなど様々です。
まず基本書の見分け方です。
どんな本がいいのかは人それぞれ好みがあるので、誰にとっても「この本が一番使いやすい!」とはいえません。
しかし、合格者の使った本を調べていくと、だいたい同じような傾向があります。
つまり、たくさん出版されている本のなかでも、わかりやすい本、使いやすい本というのは自ずと決まってくるのです。
合格者がよく使っている基本書は、予備校(TAC・Wセミナー・LEC)でも使われることのあるテキストです。
その他→司法書士 基本書 で調べる
さらに「厚い本と薄い本、どちらで勉強するか」という問題もあります。
結論からいうと、「薄い本を何回も読むほうが理解が深まる」と考えている合格者が多く、合格した年は、私もそう思いました。
以前は、日本司法学院という司法書士試験に特化した予備校があって、そのテキストが実務に直結した先例もでていて、かなり分厚い基本書がありました(今は学校自体がなくなっています)。
もちろん厚い基本書はそれなりに詳しく説明されているので、わかりやすいかもしれません。
しかし、ボリュームがありすぎて途中までしか読めない場合もあります。
そういったリスクを考えると、とくに働きながら司法書士試験を受験するなら、なるべく薄い本を何回も繰り返して読み、他の参考書を使って基本書の補足をしていくほうが効果的です。
とくに初学者の方が理解しづらいのは、ほとんどは基本書のせいではなく、読みこなす力がまだついていないということです。
それでも、焦る必要は全くありません。司法書士試験の講座を受講したり、何回もその本を読むことによって基本書を読む力は身についてくるものなんですね。
司法書士試験の基本書を理解するコツ
司法書士試験の基本書を理解することによって、試験の問題を解くことが格段に楽になります。
そのために必要な理解するコツや方法があります。
ポイントは一度で読んで、基本書を完全に理解しようと思わないことです。
基本書を3回は読む前提ですすめましょう。
まず、一回目は一気に読みます。
映画の予告編と同じで、ざっと「何が書いてあるか」がわかればよいわけです。
どんな項目があって、どんな見出しがあるのかを押さえるくらいでいいんです。
最初から、じっくり丁寧に読みだしてしまうと、そのスピード感がその後の勉強の基準になってしまう恐れがあります。
1ページ2分ぐらいで読んで、200ページのテキストで400分。
時間にして6時間ちょっとといったところです。
最後まで一気に読む
これがポイントです。最後まで一気に読む目的は、全体像の把握です。
最初の1ページ目からじっくり丁寧に読もうとすることは、なんとなく100点を目指しに行く人のパターンです。
目安としては、「流し読み以上、熟読未満」の感覚で、スピード感を強めに出して読みましょう。
そして、そのスピード感を体に覚えさせてその後の勉強に活かしていきましょう。
読書をするときに、次に何が書かれているかということが少しでもわかっているのと、そうでないのには雲泥の差があります。たった6時間ちょっとの努力です。
最初からの熟読は、結果的に、とても効率が悪いです。
次に項目ごとにかなり細かく突っ込んで読んでいきます。「なぜだろう?」「どうして?」と自問自答しながら読むわけです。言葉の意味はこのときにしっかりと覚えて、かつ理解しておくことが重要です。
二回目は焦らずじっくりと腰を据えて読み込みます。
わからないときは、理由をはっきりさせてから進みます。
「どの部分がどう理解できないのか」
この二点を明確にすることです。
合格者のほとんどの人は「疑問カード」のようなものを作っていました。
カードに疑問点とどうわからないかを書いておくのです。
そしてそのカードを常に持ち歩いて受験仲間や合格者に合った際に聞いたり、図書館で調べたりして疑問を解決するようにしていました。
自分でわかるのであれば、付箋紙や、スマホのメモ機能でもいいかもしれませんね。
最後は二回目に読んだ際に理解して得た知識をさらに高めるために読みます。
二回目は項目ごとに掘り下げて読んでいったわけなので、三回目はそれらの知識を横断的に網羅するような読み方をします。
たとえば民法の贈与は売買と比較して学習する。
使用貸借なら賃貸借と比較しながら読む。
比較したり関連事項を両方理解してこそ、すべてが関連づけられて、確実に知識は身についていくはずです。
3回目に読むときは、二回目に読んだときに理解できなかったことも、面白いほどわかってきます。
とくに民事訴訟法などの手続き関係の法律は、この典型です。
三回目は二回目の半分ぐらいの時間で読めるはずです。
「目次」はコピーして司法書士試験サブノート代わりできる
司法書士試験に必要なの知識を整理するために、「目次」はコピーしてサブノートの代わりにすると全体の体系がわかりやすくなります。
法律書は読者に少しでも無駄なく理解させようと、様々な工夫を凝らしてあります。
ですから、読者はいかにそのリズムにスムーズに乗つかるかを第一に考えるべきです。
そこでもし「この本の使い方」という所があればかならず読んでもらいたいものです。
次に、目次を必ずコピーすることをお勧めします。
この目次の使い方こそが基本書の理解のポイントです。
目次はその本のエッセンスです。
目次を見てそこに何が書かれていたかを思い出したり、これから読むところを想像したり、各章を関連付けたり……。まさに目次の利用価値は抜群です。
目次に重要事項の書き込みをしてサブノートにしてしまうこともできます。
また、本によっては大項目だけで目次が構成されているものもあります。
こんなときは、本文から中項目や小項目を抜き出して自分で詳しい目次を作ることです。
目次はテキストの見取図なので、テキストを読むときは必ずこの目次を横において、今、自分が読んでいるところがテキストのどの章のどの部分か、そしてその前後の関係を確認しながら読み進んでいくことです。
司法書士試験の基本書の知識を短期間で身につける方法
司法書士試験の基本書にある膨大な量の知識を短期間で身につける技術を身につけると、試験に必要な理解度が格段にアップします。
最近の予備校が出している基本書は、3色刷でかなり見やすくなっていますが、人それぞれ疑問に思うところやわかりにくいところは違います。
基本書に書き込む場所は人それぞれ違っていいんです。
ポイントは、書き込みするパターンを決めておくことです。
法律の初心者なら「?」マークを記入しながら読む
初めて法律の勉強をする人には「ケシゴム消し消し読書法」という方法がオススメです。
いかにも語感は軽いですが、資格取得のための読書法としては基本の基本ともいうべき方法なんですね。
基本書を読む際に短期間で知識を身につける技術の一つです。
道具は鉛筆とケシゴム。
基本書を読んでいてわからないところに鉛筆で「?」マークをつけていきます。2度、3度と繰り返し読むにしたがって、その「?」マークが理解できたらケシゴムで消していく方法です。
いつでも、どこでもできます。
ケシゴムで消すというのは実に快感です。
精神的効果も狙えるわけなのです(^_^)/~
法律の学習経験がある人は重要度をランクづけしながら読む
多少法律の勉強をしたことがある人ならテキストの記述の重要度をA・B・Cというランクで分類整理しながら読む方法がオススメです。
予備校でテキストとして基本書を使っているときには、講師によっては「AAランク」など指摘する場合もあります。
テキストを読みながら「ここは重要だ」というところの欄外に「Aマーク」を鉛筆でつけます。
次に重要なところに「Bマーク」を、そして「Cマーク」という具合です。
この方法だと試験の直前に「Aマーク」だけを拾い読みすることが可能になります。
さらに、一冊の基本書を短時間で読むことができます。
ではどんな基準で重要度をランクづけしていくのか。
まず素直に基本書に重要だと書いてある部分は「Aマーク」です。
またことの本質部分を記述している所は概ね重要な部分と考えていいですね。
次に過去の試験問題との対応です。
試験問題がたくさん出ているような所は重要ということになります。
このときあくまでもマークは鉛筆でつけます。
最初に重要と思っても学習が進むにしたがって重要でないと気づいたり、最初は重要とは思えなくても実は重要だということがわかってくる場合があるからです。
5色のラインマーカーで概念部分や数字などをマークする
法学部出身者や宅建、行政書士の受験を経験している人なら、ラインマーカーで色分けをしながら読む方法、または基本書にあらゆる情報を書き込んでいく方法がオススメです。
ラインマーカー色分け読書法は、ラインマーカーを系統的に使って基本書の効率アップを図ろうということです。
必要な色は司法書士試験の場合は五色もあれば十分です。色分けは各人の好みです。
例として、色分けしてみます。
- 黄色これは概念用に使います。
概念部分というのは「○○とは××××××のこと」というように言葉の意味を示している部分です。たとえば「不動産とは、土地およびその定着物をいう」といったところです。
司法書士試験は言葉の意味を正確につかむことが基本の基本です。 - ピンクピンクは覚えておかなければならない数字をマークします。
- 水色学説の対立の問題提起部分に使います。
「この点に関しては、Aという考え方とBという考え方の二つのの意見の争いがある。Aは……」というところです。 - オレンジオレンジはその争いのある場合の通説の見解をマークします。
- むらさき判例の見解をマークします。
これはあくまで一つの例です。いろいろな色の使い分けがあるでしょう。
学説などは、ここ最近の司法書士試験の傾向から、出題がされなくなってきているので、すっ飛ばしてもいいかもしれませんね。
しかし、あまりに分類を細分化すると、わけがわからなくなってしまうおそれがあります。
そして、一度決めたらむやみに色を変えないことです。
色分けの作業を通して頭の中が整理されて、二回目、三回目と読む時間が短縮できます。
それになんといっても、試験の直前確認の際に時間が短縮できるというメリットがあります。
基本書にあらゆる情報を書き込んでオリジナルにする
基本書にあらゆる情報を書き込んでいく「基本書ターミナル法」は、基本書とノートと資料集との一体化ともいえます。
すべての情報を一元化するのです。
この方法は人によって様々なやり方があると思うので、一つの例をあげておきます。
基本書を読んでいて、「この部分は前章の○○と関連するな」とわかったら、「△△ページ参照」とか、「**ページ比較」というふうに基本書に書き込んでいく。
- 基本書のそのページにある重要語句を赤ペンで欄外に書いておく。
- 参考書などで役立つ記載があったら基本書の該当個所にテープでコピーを貼っておく。もしくは要約したものを書き込んでおく。
- 過去の問題の出題状況や典型的な問題を書き込む。
- 複雑でわかりにくいところを自分で図解して書き込んでおく。
- 結論しか書いてないところは自分で考えた理由を書き込む。
といった方法です。
最近ではネットでクラウドを利用した書き込み方法などもありますが、司法書士試験に限ってはアナログのように自分の手を利用することがオススメです。
現状の試験ではパソコンで解答できないですからね。
最終的なイメージとしては、試験の直前に短時間で見返す基本書にすることです。
汚くてもいいんです。強弱がわかれば、自分だけがわかればいい基本書です。
試験直前の緊張の日々に、この何でも書き込まれた基本書があると、かなり精神的には楽になりますよ。
→司法書士試験の講座がある学校を丁寧に紹介しています。